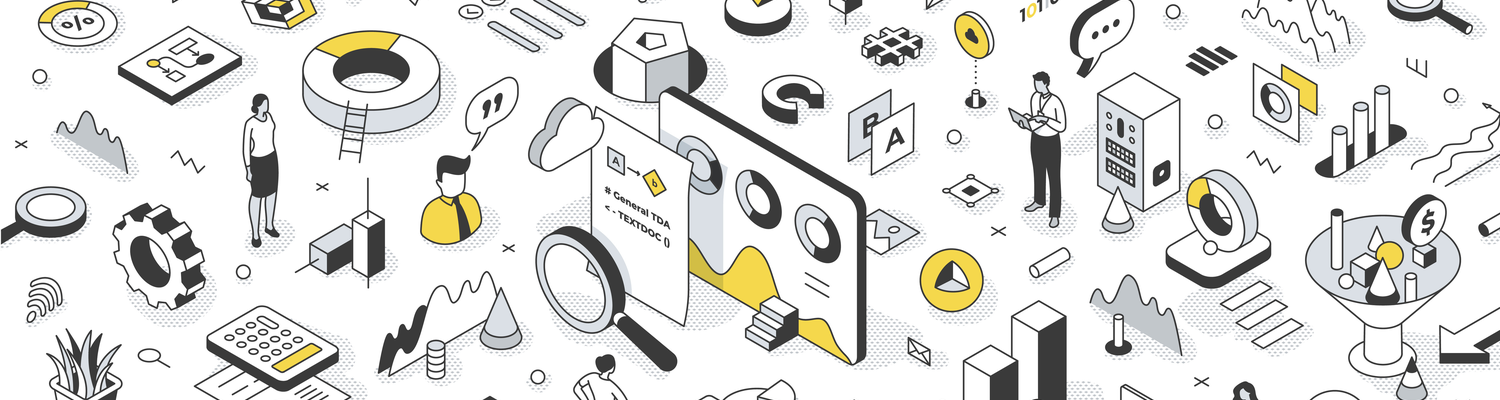
SIGNATE コンペ参戦記録

R
就活大学生
SIGNATE コンペ参戦記録
こんにちは、3CA の R です。 就活の早期化にビビりつつ、インターン特典を狙ってコンペに挑戦したものの、見事に散った話をお届けします。
2025 年夏に開催された MUFG Data Science Challenge 2025 に参加しました。 最終順位は Public 4 位 → Private 79 位 と悔しい結果に終わりましたが、 学びが多かったのでまとめます。
※ コンペは終了しています
Public / Private スコアとは
機械学習コンペでは、テストデータが 2 つに分かれています。
- Public:コンペ期間中に見えるスコア(テストデータの一部で評価)
- Private:最終順位を決めるスコア(残りのテストデータで評価)
Public で良いスコアが出ても、Private で大きく順位が下がることを「シェイクダウン」と呼びます。 今回はまさにその典型例でした。
アプローチの全体像
-
ベースライン
- CatBoost / LightGBM / XGBoost の 3 本モデルを学習
- OOF(Out-of-Fold)予測を保存してブレンド・スタッキングに利用
-
工夫した点
- ロジットブレンド + OOF しきい値最適化
- スタッキング(Logistic Regression + メタ特徴量 + L1 正則化)
- 複数アンサンブルの多数決提出
-
失敗した点
- CV(交差検証)の分布が Public / Private とズレており、Public に過学習してしまった(CV 弱い問題)
工夫 1: ロジットブレンド + しきい値最適化
単純平均よりもロジット変換して線形結合が有効でした。 さらに F1 スコアを最大化するしきい値を OOF 上で探索し、Test にはその設定を適用しました。
# ロジット変換
def logit(p, eps=1e-9):
p = np.clip(p, eps, 1-eps)
return np.log(p/(1-p))
# F1最適化のしきい値探索
best_thr, best_f1 = best_f1_threshold(y_true, oof_proba)工夫 2: スタッキング(LR + メタ特徴量 + L1 正則化)
Cat/LGBM/XGB の確率をそのまま使うだけでなく、「確率」「ロジット」「ランク」「統計値」をメタ特徴量として加えました。 さらに Logistic Regression の L1 正則化で不要特徴量を自動で刈り取り、安定性を高めました。
# メタ特徴量の生成
def meta_features(pred_list):
P = np.vstack(pred_list).T # 確率
L = logit(P) # ロジット
R = row_ranks(P) # ランク
# 統計量(平均、標準偏差、最小・最大値)も追加
# L1正則化でスタッキング
clf = LogisticRegression(penalty="l1", C=2.0, class_weight="balanced")結果と反省
最終スコア
- Public: 0.6616(4 位)
- Private: 0.64 前後(79 位)
反省点
- CV の組み方が甘く、Public に最適化しすぎて Private で崩壊
- 特に分布差(train/test, Public/Private)に敏感な F1 評価で痛手
学び
-
OOF の設計と活用がすべての土台 → CV 設計を誤ると、Public スコアは当てにならない
-
アンサンブルは「確率 → ロジット」「特徴量の追加」が効く → 特に rank 特徴量はシンプルで強力
-
しきい値最適化は必須 → F1 指標では threshold tuning が最後の仕上げになる
ChatGPT 活用法
今回のコンペではChatGPT を最大限活用しました。
-
コード自動生成・修正
- ロジットブレンド、スタッキング、アルファブレンド、キャリブレーションなどのスクリプトを会話しながら設計・改善
- エラーが出たときも即座に修正案を提示してもらい、試行サイクルを高速化
-
戦略相談
- 次の一手を ChatGPT に聞きながら、提出回数を無駄にせず進められた
- ブレンド/スタッキング/キャリブレーションの順序を議論しながら選べた
所感: ChatGPT に手を動かす部分を任せ、自分は意思決定と検証に集中できたのが大きな収穫でした。 特に Kaggle/SIGNATE のように「提出回数制限」がある環境では、効率が段違いに向上します。
まとめ
今回は入賞には届きませんでしたが、
- ロジットブレンド
- スタッキング + メタ特徴量
- OOF ベースのしきい値最適化
- ChatGPT のフル活用
といった工夫でPublic 5 位圏内を経験できました。
Private 崩壊も含めて、今後の自分や読者にとって貴重な教訓になりました。 次は CV 設計にもっとこだわって挑戦したいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました!

